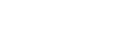【国立国際美術館】特別展「ノー・バウンダリーズ」2025年2月22日(土)から6月1日(日)まで開催
現代社会におけるさまざまな「境界」の枠組みを解体し、多様性や共生の新たな価値を国内外の作家が提案
私たちの社会には、さまざまなバウンダリー(境界)が存在します。国境や土地の境界など物理的なものから、心理的、社会的、文化的なものまで多岐にわたり、私たちの行動、思考、価値観を形成する輪郭になります。今日の物理的・社会的な境界はグローバル化やテクノロジーの進化によって様変わりしていますが、その一方で新たな分断や排除を生み出しています。
こうした現代社会において、アーティストは作品や表現活動を通じアイデンティティ、文化、ジェンダー、物理的空間や時間など、社会において概念化された境界を軽やかに超越し、多様な価値観が交差する場を創出しています。
「ノー・バウンダリーズ」展と題した本展覧会では、国立国際美術館が所蔵する20 余名の国内外で活躍する現代美術作家による作品を通して、現代社会におけるさまざまな「境界」をテーマに、私たちの日常や価値観がいかに形成されているのかを可視化するとともに、私たちが「境界」と呼ぶ既存の枠組みを解体し、新たな視座の提示を試みます。展覧会を通して、鑑賞者が既成概念を超え、多様性や共生の価値を再認識する機会となることを目指します。
出品作家 ※変更となる場合があります
クリスチャン・ボルタンスキー、フェリックス・ゴンザレス=トレス、廣直高、鎌田友介、マイク・ケリー、キム・ボム、松井智惠、三島喜美代、ミヤギフトシ、森村泰昌、アリン・ルンジャーン、カリン・ザンダー、シンディ・シャーマン、田島美加、田中功起、ヴォルフガング・ティルマンス、ヤン・ヴォー、エヴェリン・タオチェン・ワン、ミン・ウォン、山城知佳子、やなぎみわ
本展の見どころ
当館は1970 年に開催された日本万国博覧会に際して建設された万国博美術館の建物を活用し、1977 年に開館しました。折りしも本展の会期中、2025 年4 月から大阪・関西万博が開催されます。国内外から最先端技術が集結し、経済発展や社会的課題の解決に取り組むこの時期に合わせて、当館では多様な価値観の作家たちが提案するさまざまな「境界」を通し、新たな社会の日常や価値観を提案します。
シンガポール出身独・ベルリン在住のミン・ウォンは、映画や演劇を通じて文化的な翻訳、引用やアイデンティティをテーマにした作品でよく知られています。
ヴェネチア・ビエンナーレに出品し高い評価を獲得した映像《ライフ・オブ・イミテーション》(2009) は、発表当時に人種、映画、ジェンダーの問題が浮き彫りとなったハリウッド映画『イミテーション・オブ・ライフ』へのオマージュとして制作されました。シンガポールの主要3 民族(中華系、マレー系、インド系)による俳優たちが登場人物を演じており、人種とジェンダーの問題に加えてユーモアも含みながら、現在のグローバル化した社会おける文化的規範からの逸脱も見え隠れします。
ミン・ウォン《ライフ・オブ・イミテーション》2009 年 2 チャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(HD、カラー、サウンド)国立国際美術館蔵 (C) Ming Wong
中国・成都出身オランダ・ロッテルダム在住のエヴェリン・タオチェン・ワンは、多岐にわたるメディアの表現により高い評価を獲得していますが、油彩画《トルコ人女性たちのブラックベリー》(2023) では、伝統的な中国の書画と西洋美術の絵画技術を柔軟に取り込むとともに、ジェンダー問題や植民地史をテーマに浮かび上がらせます。
エヴェリン・タオチェン・ワン《トルコ人女性たちのブラックベリー》2023 年 油彩、鉛筆、石膏、カンバス 国立国際美術館蔵 (C) Evelyn Taocheng Wang
タイ・バンコク出身在住のアリン・ルンジャーンは、映像《246247596248914102516... そして誰もいなくなった》(2017) において、ヒトラーの最後の面会者がタイの民主化革命に関わったメンバーのタイ人であるという歴史的事実と、自身の父親がかつてドイツ企業で働いた経験を持つという私的側面を重ね合わせることで、時間そして地理的境界を再構築し境界の拡張を試みます。
アリン・ルンジャーン《246247596248914102516 ... そして誰もいなくなった》2017 年シングルチャンネル・ヴィデオ(HD、カラー、サウンド)国立国際美術館蔵 (C) Arin Rungjang
日本人の両親のもとロサンゼルスに生まれ現在はニューヨーク在住の田島美加は、ジャンル横断的な制作姿勢が見られます。近年はエリク・サティが提唱した生活空間に溶け込む音楽にちなんだ「アールダムーブルモン(Art dʼ Ameublement)」シリーズや、様々な場所、条件下で録音した音源をデジタルデータに変換し。得られた図像データを構図にジャガード織へと変容させる「ネガティブ・エントロピー(Negative Entropy)」シリーズ、有機的な形態が特徴的なガラス作品など、環境、社会、テクノロジーを核に、それぞれの境界を融解させながら表現することで深淵な考察を示しています。
田島美加《アニマ11》2022 年 黒ガラス、ブロンズ製ジェットノズル 国立国際美術館蔵 Photo by Charles Benton(C) Mika Tajima
このほか、ヴォルフガング・ティルマンス《アストロ・クラスト、a》(2012) やヤン・ヴォー《無題》(2019-20) などもご紹介します。
ヴォルフガング・ティルマンス《アストロ・クラスト、a》2012年 インクジェットプリント、クリップ 国立国際美術館蔵 (C) Wolfgang Tillmans
ヤン・ヴォー《無題》2019-20年 国立国際美術館蔵 「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景(国立国際美術館、2020 年)撮影:福永一夫(C) Danh Vo
関連イベント
ギャラリー・トーク等開催予定。詳細は決まり次第、当館ウェブサイト等でお知らせします。
展覧会ページURL
https://www.nmao.go.jp/events/event/20250222_noboundaries/
開催概要
会期:2025 年2 月22 日(土)‒ 6 月1 日(日)
会場:国立国際美術館 地下3 階展示室(〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-55)
開館時間:10:00 ‒ 17:00、金曜・土曜は20:00 まで ※入場は閉館の30 分前まで
休館日:月曜日(ただし2 月24 日、5 月5 日は開館)、2 月25 日(火)、5 月7 日(水)
主催:国立国際美術館
協賛:ダイキン工業現代美術振興財団
観 覧 料:一般1,200 円(1,000 円)大学生700 円(600 円)
( )内は 20 名以上の団体及び夜間割引料金(対象時間:金曜・土曜の 17:00―20:00)
高校生以下・18 歳未満無料(要証明)・心身に障がいのある方とその付添者1 名無料(要証明)
本料金で、同時開催のコレクション展もご覧いただけます。
交通アクセスはこちら
https://www.nmao.go.jp/visit/admission/
一般のお客様からのお問い合わせ先
国立国際美術館 TEL:06-6447-4680(代表)
https://www.nmao.go.jp/
私たちの社会には、さまざまなバウンダリー(境界)が存在します。国境や土地の境界など物理的なものから、心理的、社会的、文化的なものまで多岐にわたり、私たちの行動、思考、価値観を形成する輪郭になります。今日の物理的・社会的な境界はグローバル化やテクノロジーの進化によって様変わりしていますが、その一方で新たな分断や排除を生み出しています。
こうした現代社会において、アーティストは作品や表現活動を通じアイデンティティ、文化、ジェンダー、物理的空間や時間など、社会において概念化された境界を軽やかに超越し、多様な価値観が交差する場を創出しています。
「ノー・バウンダリーズ」展と題した本展覧会では、国立国際美術館が所蔵する20 余名の国内外で活躍する現代美術作家による作品を通して、現代社会におけるさまざまな「境界」をテーマに、私たちの日常や価値観がいかに形成されているのかを可視化するとともに、私たちが「境界」と呼ぶ既存の枠組みを解体し、新たな視座の提示を試みます。展覧会を通して、鑑賞者が既成概念を超え、多様性や共生の価値を再認識する機会となることを目指します。
出品作家 ※変更となる場合があります
クリスチャン・ボルタンスキー、フェリックス・ゴンザレス=トレス、廣直高、鎌田友介、マイク・ケリー、キム・ボム、松井智惠、三島喜美代、ミヤギフトシ、森村泰昌、アリン・ルンジャーン、カリン・ザンダー、シンディ・シャーマン、田島美加、田中功起、ヴォルフガング・ティルマンス、ヤン・ヴォー、エヴェリン・タオチェン・ワン、ミン・ウォン、山城知佳子、やなぎみわ
本展の見どころ
当館は1970 年に開催された日本万国博覧会に際して建設された万国博美術館の建物を活用し、1977 年に開館しました。折りしも本展の会期中、2025 年4 月から大阪・関西万博が開催されます。国内外から最先端技術が集結し、経済発展や社会的課題の解決に取り組むこの時期に合わせて、当館では多様な価値観の作家たちが提案するさまざまな「境界」を通し、新たな社会の日常や価値観を提案します。
シンガポール出身独・ベルリン在住のミン・ウォンは、映画や演劇を通じて文化的な翻訳、引用やアイデンティティをテーマにした作品でよく知られています。
ヴェネチア・ビエンナーレに出品し高い評価を獲得した映像《ライフ・オブ・イミテーション》(2009) は、発表当時に人種、映画、ジェンダーの問題が浮き彫りとなったハリウッド映画『イミテーション・オブ・ライフ』へのオマージュとして制作されました。シンガポールの主要3 民族(中華系、マレー系、インド系)による俳優たちが登場人物を演じており、人種とジェンダーの問題に加えてユーモアも含みながら、現在のグローバル化した社会おける文化的規範からの逸脱も見え隠れします。
ミン・ウォン《ライフ・オブ・イミテーション》2009 年 2 チャンネル・ヴィデオ・インスタレーション(HD、カラー、サウンド)国立国際美術館蔵 (C) Ming Wong
中国・成都出身オランダ・ロッテルダム在住のエヴェリン・タオチェン・ワンは、多岐にわたるメディアの表現により高い評価を獲得していますが、油彩画《トルコ人女性たちのブラックベリー》(2023) では、伝統的な中国の書画と西洋美術の絵画技術を柔軟に取り込むとともに、ジェンダー問題や植民地史をテーマに浮かび上がらせます。
エヴェリン・タオチェン・ワン《トルコ人女性たちのブラックベリー》2023 年 油彩、鉛筆、石膏、カンバス 国立国際美術館蔵 (C) Evelyn Taocheng Wang
タイ・バンコク出身在住のアリン・ルンジャーンは、映像《246247596248914102516... そして誰もいなくなった》(2017) において、ヒトラーの最後の面会者がタイの民主化革命に関わったメンバーのタイ人であるという歴史的事実と、自身の父親がかつてドイツ企業で働いた経験を持つという私的側面を重ね合わせることで、時間そして地理的境界を再構築し境界の拡張を試みます。
アリン・ルンジャーン《246247596248914102516 ... そして誰もいなくなった》2017 年シングルチャンネル・ヴィデオ(HD、カラー、サウンド)国立国際美術館蔵 (C) Arin Rungjang
日本人の両親のもとロサンゼルスに生まれ現在はニューヨーク在住の田島美加は、ジャンル横断的な制作姿勢が見られます。近年はエリク・サティが提唱した生活空間に溶け込む音楽にちなんだ「アールダムーブルモン(Art dʼ Ameublement)」シリーズや、様々な場所、条件下で録音した音源をデジタルデータに変換し。得られた図像データを構図にジャガード織へと変容させる「ネガティブ・エントロピー(Negative Entropy)」シリーズ、有機的な形態が特徴的なガラス作品など、環境、社会、テクノロジーを核に、それぞれの境界を融解させながら表現することで深淵な考察を示しています。
田島美加《アニマ11》2022 年 黒ガラス、ブロンズ製ジェットノズル 国立国際美術館蔵 Photo by Charles Benton(C) Mika Tajima
このほか、ヴォルフガング・ティルマンス《アストロ・クラスト、a》(2012) やヤン・ヴォー《無題》(2019-20) などもご紹介します。
ヴォルフガング・ティルマンス《アストロ・クラスト、a》2012年 インクジェットプリント、クリップ 国立国際美術館蔵 (C) Wolfgang Tillmans
ヤン・ヴォー《無題》2019-20年 国立国際美術館蔵 「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景(国立国際美術館、2020 年)撮影:福永一夫(C) Danh Vo
関連イベント
ギャラリー・トーク等開催予定。詳細は決まり次第、当館ウェブサイト等でお知らせします。
展覧会ページURL
https://www.nmao.go.jp/events/event/20250222_noboundaries/
開催概要
会期:2025 年2 月22 日(土)‒ 6 月1 日(日)
会場:国立国際美術館 地下3 階展示室(〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-55)
開館時間:10:00 ‒ 17:00、金曜・土曜は20:00 まで ※入場は閉館の30 分前まで
休館日:月曜日(ただし2 月24 日、5 月5 日は開館)、2 月25 日(火)、5 月7 日(水)
主催:国立国際美術館
協賛:ダイキン工業現代美術振興財団
観 覧 料:一般1,200 円(1,000 円)大学生700 円(600 円)
( )内は 20 名以上の団体及び夜間割引料金(対象時間:金曜・土曜の 17:00―20:00)
高校生以下・18 歳未満無料(要証明)・心身に障がいのある方とその付添者1 名無料(要証明)
本料金で、同時開催のコレクション展もご覧いただけます。
交通アクセスはこちら
https://www.nmao.go.jp/visit/admission/
一般のお客様からのお問い合わせ先
国立国際美術館 TEL:06-6447-4680(代表)
https://www.nmao.go.jp/