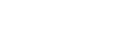金継ぎ体験が恋のはじまり?婚活男女10名のご縁をつなぐ、金継ぎマッチングイベントの結果は
割れた陶器を修復する金継ぎ(きんつぎ)は、破片だけでなく男女もつなぐのか?婚活業界大手のIBJと、金継ぎ専門のつぐつぐが共催した、新しい婚活イベントの結果を発表します。
金継ぎするシーグラス・シー陶器を選ぶ様子
生涯ずっと一緒にいる人だから、見た目や肩書きより、内面がぴったり合う人と結婚したい。
そう願う人は多いですが、日本では若者の結婚数が減少中。
そのため最近は様々な恋愛マッチングサービスがありますが、短い時間で相手の性格を見極めるのは簡単ではありません。
そこで私たちは、食事や会話だけでなく、共通の趣味・体験を通じて相手の隠れた魅力を引き出す、新しい出会い方に着目しました。
同じ作業をすることで、普段見えにくい内面が自然と浮かび上がってくると考えたからです。
室町時代から伝わる金継ぎ
ヒントを得たのが、室町時代から伝わる日本の伝統金継ぎ。割れた陶器を、漆と金で美しくつなぎ直す技法です。
株式会社つぐつぐ (本社:東京都渋谷区/代表取締役:俣野由季、以下「つぐつぐ」) の金継ぎワークショップにも、カップルや家族、離れて暮らす友人同士が多く参加しています。
この金継ぎワークショップは、修復作業にとどまらず、心の距離が縮まる「つながる体験」として好評です。
参加者同士が仲を深め、修復を通して絆を育む姿から、「金継ぎは器だけでなく心もつなげるのでは?」という仮説が生まれました。
そこで、婚活業界大手の株式会社IBJ(以下、IBJ)と、金継ぎ専門のつぐつぐがタッグを組み、今までにない金継ぎによる婚活イベントが誕生しました。
金継ぎとは?
金継ぎビフォー・アフター
金継ぎとは、15~16世紀の室町時代に日本で発祥したといわれる伝統技法です。
割れた陶磁器を漆で繋ぎ合わせ、その継ぎ目を金で彩ることで、あえて傷跡を美しく際立たせるのが特徴です。
修復後の器は、割れる前の姿よりも芸術性が増し、いっそう価値が高まるとされています。
この考え方は、日本独特の「侘び寂び」の美意識──古く不完全なものの中に美を見出す精神──に深く根ざしています。
近年では海外からも大きな注目を集め、コロナ禍をきっかけに日本国内でもブームが広がりました。
つぐつぐの金継ぎ教室には、月間のべ300名以上の方が参加し、ご自身の器を新たなお気に入りへと蘇らせています。
金継ぎマッチングイベントの様子
金継ぎマッチングイベントの様子
2025年7月19日(土)、都内IBJ会議室にて、金継ぎ風体験×マッチングありの婚活パーティーを開催しました。
参加者は20~30代の女性6名・男性4名の合計10名。
参加者の募集開始後、すぐに女性枠が満席になるほどの人気ぶりでした。
当イベントでは1時間で作品を完成させるため、漆ではなく合成樹脂を用いた金継ぎ“風”の箸置き作りを実施しました。
作業の合間には金継ぎの歴史に関するレクチャーを交え、男女で自然と会話する時間も設けました。
断面がぴったり合う石を選ぶ様子
世界にひとつだけの金継ぎ箸置きを作ります。
まずはじめに、断面がぴったり合う石を選びあいました。
石同士を合わせて確認する様子
つぐつぐが提供するのは、シーグラスとシー陶器。これらは海で拾われたガラス片や陶片です。
遠い昔、ゴミとして捨てられたものが、約100年以上も海で漂流するうちに、小さくなったものです。
時を重ねるほど、角が丸まり、少しずつ小さくなる--まるで人生を表しているようです。
異質なシーグラスとシー陶器を組み合わせるのもオシャレ
この自然の海洋ゴミを、金継ぎ風におしゃれにアップサイクル。
最初は緊張していた方も、選ぶ工程で自分らしい石に出会います。
ぴったり合う石を探して、男女で協力し合う姿も見られました。
継ぎ目に金を慎重に塗るシーン
ハイライトは、継ぎ目に金を塗るシーン。
息をのむほど集中が高まり、会場は一瞬、静寂に包まれました。
細部にまで神経を行き渡らせる真剣な表情には、お互いの誠実さやこだわりがにじみ出ていました。
作業を通じて自然と会話が弾む
作品を完成させたあとは、お互いの箸置きを見せ合って談笑。
それぞれのセンスや個性で会話が盛り上がりました。
自然な流れで連絡先を交換するペアも誕生しました。
1組のカップルが生まれて、安堵。
そして見事、1組のカップリングが成立!
その後のトークタイムを楽しんでいただきました。
通常のお見合いでは知ることのできない、相手の価値観を手作業から感じ取れたことが、自然なご縁につながったようです。
参加者の個性が光る作品例1.
参加者の個性が光る作品例2.
なぜ金継ぎで恋がはじまるのか?
金継ぎワークショップを活用した婚活イベントは今回初めての開催のため、確かな傾向はわかりません。
しかしつぐつぐは「金継ぎは人間の絆を強くする」「恋のきっかけになる」と信じています。
東京にあるつぐつぐの店舗での金継ぎワークショップの様子
つぐつぐの金継ぎ教室やワークショップに参加される方は、モノを大切にする気持ちや、手間暇をかけて生活を豊かにしたいと願う、共通の特徴があります。
効率だけを求めるのではなく、割れた器をゆっくり直す過程そのものを楽しみ、修復を趣味とされる方も少なくありません。
修復のたびに喜びを感じる「モノへの向き合い方」は、そのまま「人への向き合い方」に映ります。
こうした価値観を共有する異性同士は、自然と惹かれ合う可能性があると考えています。
最近は金継ぎ教室への参加者の年齢層が下がり、20代の方も増えてきました。
性別に関しては、つぐつぐの金継ぎ教室に通われる方の約9割が女性ですが、「金継ぎ男子」も増加中です。
「金継ぎが趣味」という響きが持つ品の良さが、異なる世代・性別を引き寄せているのでしょう。
モノを大切にし、修復の過程を楽しむ価値観を共有できるカップルは、仮にケンカをしても互いのヒビに向き合い、修復して関係を深めていくはず。
こうした理由から、金継ぎは単なる手作業を超え、人と人のご縁をつなぐ場になると考えています。
コロナ後、金継ぎの捉え方に変化が
金継ぎは、大切な器を捨てたくないという思いから、再使用を目的に行われるのが一般的でした。
「金継ぎするほど高い器を持っていない」とおっしゃる方も多いですが、つぐつぐで金継ぎする器は決して高額なものばかりではありません。
日常のお茶碗の金継ぎ
たとえば、手に入れた時の価格は安くても二度と手に入らない作家の作品、亡き母が使っていたお茶碗、娘が初めて幼稚園で作ってくれたマグカップ、彼氏と初めての旅行で買った陶器のタンブラー、引き出物のペアの片方が割れてしまったボウルなど、日常の品ばかりです。
一方で、近年は「修復する過程そのもの」を楽しむ方が増えています。
忙しさを忘れて、黙々と手先に集中する時間は、瞑想に近い感覚があります。
さらに、モノを直す過程で過去を振り返り、内省し、自分の心の傷にもそっと向き合える――そんな金継ぎの哲学に共感する人が増えています。
その結果、金継ぎは海外からも “Bonding Experience(=絆を深める体験)” と評価され、チームビルディングや研修に取り入れられる事例が広がっています。
つぐつぐでも企業からのご依頼が増加しており、会議室やホテルへ出向く出張金継ぎワークショップを実施しています。
昨年は80名規模のワークショップを行い、日本の伝統文化を感じながら、チームメイト同士の親交を深める機会を提供しました。
SDGsにかなった伝統技法としても注目
金継ぎは、サステナブルな伝統技法としても注目されています。
壊れたものを捨てずに直して使い続ける姿勢は、SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」に貢献します。
今回の婚活イベントでも、シーグラスやシー陶器(海岸で見つかるガラス片・陶器片)を組み合わせ、金継ぎ風の箸置きへとアップサイクルする簡易ワークショップを実施しました。
欠片にシーグラスを呼び継ぎした器
本来の金継ぎは同じ器の破片同士をつなぎますが、欠片が大きく足りない場合には、別の器の破片を合わせて継ぎ直す「呼び継ぎ」という技法があります。
呼び継ぎは、異質なもの同士が「一度くっついたら離れない」とされる縁起物で、平和の象徴や、家庭の調和を願って施されてきたともいわれています。
そうした背景を踏まえ、今回のワークショップで生まれた、世界にひとつの呼び継ぎ箸置きが、将来一緒に食卓を囲むご縁へとつながっていくことを願っています。
つぐつぐでは、通常は天然の漆を用いた伝統金継ぎを行っています。
しかし伝統金継ぎは工程が多く難易度も高いため、短時間で行うのが難しく、「敷居が高そう」というお声も少なくありません。
そこで入口として、今回のような金継ぎ風のワークショップもご用意しています。
なお、金継ぎ風のワークショップで使用する接着剤は食器への直接使用を想定していません。
そのため、実際に食器を修復する際は、必ず食器にも安心して使える自然の漆による伝統金継ぎを採用します。
つぐつぐでは、今回のイベントのような1時間の金継ぎ風のワークショップだけでなく、90分の伝統金継ぎワークショップ、趣味として長く通える伝統金継ぎ教室を行い、一般の方でも金継ぎできるように指導しています。
そして「自分では難しい」と感じる方のために、プロ金継ぎ師に金継ぎを依頼できる、修理サービスも提供しています。
大切な器が割れてしまったとき、「捨てるしかない」と考えるのではなく、金継ぎしてまた長く使う選択肢があることを知っていいただければ幸いです。
最後に
この記事を読んで、金継ぎについて少し興味を持ったけど、本物の金継ぎ器をまだご覧になったことがない方は多いと思います。
つぐつぐのプロ金継ぎ師が金継ぎし、さらに芸術的になった器
9月11日~15日、東京・新御茶ノ水駅近くで「つぐつぐ金継ぎ作品展2025」を開催します。
昨年に続く2回目の今年は規模を拡大し、つぐつぐの金継ぎ教室の生徒とプロの金継ぎ師・漆芸家による、合計100点以上の金継ぎ器を展示する予定です。
それだけではありません。
会期中に、今回のイベントと同じ金継ぎ風ワークショップを当日受付でご体験いただけます(有料) 。
さらに、割れた器をご持参いただくと、予約制の無料お見積り相談会で修理可否と修理費用をご案内し、ご希望に応じて金継ぎ師への修理依頼も承ります(要予約/見積無料)。
作品展示では、ただ美しく個性的な作品を並べるだけではありません。
「なぜ、手間暇をかけてまで直すのか?」――出展者それぞれの“金継ぎドラマ”も掲示し、金継ぎの価値をわかりやすくお届けします。
プロの金継ぎ師・漆芸家による金継ぎ作品は、購入もできます。
金継ぎをブームで終わらせず、文化にする。
つぐつぐは、モノだけでなく、伝統を継承し、あなたの心もつないでいきます。
つぐつぐ金継ぎ作品展2025の詳しい情報はこちら
https://ocha-navi.solacity.jp/gallery/event/563.html
これからも、金継ぎを通して、世の中に新しくて面白い企画をお届けし、
伝統をつないでいきます。
■ IBJ Matching
https://www.partyparty.jp/
金継ぎするシーグラス・シー陶器を選ぶ様子
生涯ずっと一緒にいる人だから、見た目や肩書きより、内面がぴったり合う人と結婚したい。
そう願う人は多いですが、日本では若者の結婚数が減少中。
そのため最近は様々な恋愛マッチングサービスがありますが、短い時間で相手の性格を見極めるのは簡単ではありません。
そこで私たちは、食事や会話だけでなく、共通の趣味・体験を通じて相手の隠れた魅力を引き出す、新しい出会い方に着目しました。
同じ作業をすることで、普段見えにくい内面が自然と浮かび上がってくると考えたからです。
室町時代から伝わる金継ぎ
ヒントを得たのが、室町時代から伝わる日本の伝統金継ぎ。割れた陶器を、漆と金で美しくつなぎ直す技法です。
株式会社つぐつぐ (本社:東京都渋谷区/代表取締役:俣野由季、以下「つぐつぐ」) の金継ぎワークショップにも、カップルや家族、離れて暮らす友人同士が多く参加しています。
この金継ぎワークショップは、修復作業にとどまらず、心の距離が縮まる「つながる体験」として好評です。
参加者同士が仲を深め、修復を通して絆を育む姿から、「金継ぎは器だけでなく心もつなげるのでは?」という仮説が生まれました。
そこで、婚活業界大手の株式会社IBJ(以下、IBJ)と、金継ぎ専門のつぐつぐがタッグを組み、今までにない金継ぎによる婚活イベントが誕生しました。
金継ぎとは?
金継ぎビフォー・アフター
金継ぎとは、15~16世紀の室町時代に日本で発祥したといわれる伝統技法です。
割れた陶磁器を漆で繋ぎ合わせ、その継ぎ目を金で彩ることで、あえて傷跡を美しく際立たせるのが特徴です。
修復後の器は、割れる前の姿よりも芸術性が増し、いっそう価値が高まるとされています。
この考え方は、日本独特の「侘び寂び」の美意識──古く不完全なものの中に美を見出す精神──に深く根ざしています。
近年では海外からも大きな注目を集め、コロナ禍をきっかけに日本国内でもブームが広がりました。
つぐつぐの金継ぎ教室には、月間のべ300名以上の方が参加し、ご自身の器を新たなお気に入りへと蘇らせています。
金継ぎマッチングイベントの様子
金継ぎマッチングイベントの様子
2025年7月19日(土)、都内IBJ会議室にて、金継ぎ風体験×マッチングありの婚活パーティーを開催しました。
参加者は20~30代の女性6名・男性4名の合計10名。
参加者の募集開始後、すぐに女性枠が満席になるほどの人気ぶりでした。
当イベントでは1時間で作品を完成させるため、漆ではなく合成樹脂を用いた金継ぎ“風”の箸置き作りを実施しました。
作業の合間には金継ぎの歴史に関するレクチャーを交え、男女で自然と会話する時間も設けました。
断面がぴったり合う石を選ぶ様子
世界にひとつだけの金継ぎ箸置きを作ります。
まずはじめに、断面がぴったり合う石を選びあいました。
石同士を合わせて確認する様子
つぐつぐが提供するのは、シーグラスとシー陶器。これらは海で拾われたガラス片や陶片です。
遠い昔、ゴミとして捨てられたものが、約100年以上も海で漂流するうちに、小さくなったものです。
時を重ねるほど、角が丸まり、少しずつ小さくなる--まるで人生を表しているようです。
異質なシーグラスとシー陶器を組み合わせるのもオシャレ
この自然の海洋ゴミを、金継ぎ風におしゃれにアップサイクル。
最初は緊張していた方も、選ぶ工程で自分らしい石に出会います。
ぴったり合う石を探して、男女で協力し合う姿も見られました。
継ぎ目に金を慎重に塗るシーン
ハイライトは、継ぎ目に金を塗るシーン。
息をのむほど集中が高まり、会場は一瞬、静寂に包まれました。
細部にまで神経を行き渡らせる真剣な表情には、お互いの誠実さやこだわりがにじみ出ていました。
作業を通じて自然と会話が弾む
作品を完成させたあとは、お互いの箸置きを見せ合って談笑。
それぞれのセンスや個性で会話が盛り上がりました。
自然な流れで連絡先を交換するペアも誕生しました。
1組のカップルが生まれて、安堵。
そして見事、1組のカップリングが成立!
その後のトークタイムを楽しんでいただきました。
通常のお見合いでは知ることのできない、相手の価値観を手作業から感じ取れたことが、自然なご縁につながったようです。
参加者の個性が光る作品例1.
参加者の個性が光る作品例2.
なぜ金継ぎで恋がはじまるのか?
金継ぎワークショップを活用した婚活イベントは今回初めての開催のため、確かな傾向はわかりません。
しかしつぐつぐは「金継ぎは人間の絆を強くする」「恋のきっかけになる」と信じています。
東京にあるつぐつぐの店舗での金継ぎワークショップの様子
つぐつぐの金継ぎ教室やワークショップに参加される方は、モノを大切にする気持ちや、手間暇をかけて生活を豊かにしたいと願う、共通の特徴があります。
効率だけを求めるのではなく、割れた器をゆっくり直す過程そのものを楽しみ、修復を趣味とされる方も少なくありません。
修復のたびに喜びを感じる「モノへの向き合い方」は、そのまま「人への向き合い方」に映ります。
こうした価値観を共有する異性同士は、自然と惹かれ合う可能性があると考えています。
最近は金継ぎ教室への参加者の年齢層が下がり、20代の方も増えてきました。
性別に関しては、つぐつぐの金継ぎ教室に通われる方の約9割が女性ですが、「金継ぎ男子」も増加中です。
「金継ぎが趣味」という響きが持つ品の良さが、異なる世代・性別を引き寄せているのでしょう。
モノを大切にし、修復の過程を楽しむ価値観を共有できるカップルは、仮にケンカをしても互いのヒビに向き合い、修復して関係を深めていくはず。
こうした理由から、金継ぎは単なる手作業を超え、人と人のご縁をつなぐ場になると考えています。
コロナ後、金継ぎの捉え方に変化が
金継ぎは、大切な器を捨てたくないという思いから、再使用を目的に行われるのが一般的でした。
「金継ぎするほど高い器を持っていない」とおっしゃる方も多いですが、つぐつぐで金継ぎする器は決して高額なものばかりではありません。
日常のお茶碗の金継ぎ
たとえば、手に入れた時の価格は安くても二度と手に入らない作家の作品、亡き母が使っていたお茶碗、娘が初めて幼稚園で作ってくれたマグカップ、彼氏と初めての旅行で買った陶器のタンブラー、引き出物のペアの片方が割れてしまったボウルなど、日常の品ばかりです。
一方で、近年は「修復する過程そのもの」を楽しむ方が増えています。
忙しさを忘れて、黙々と手先に集中する時間は、瞑想に近い感覚があります。
さらに、モノを直す過程で過去を振り返り、内省し、自分の心の傷にもそっと向き合える――そんな金継ぎの哲学に共感する人が増えています。
その結果、金継ぎは海外からも “Bonding Experience(=絆を深める体験)” と評価され、チームビルディングや研修に取り入れられる事例が広がっています。
つぐつぐでも企業からのご依頼が増加しており、会議室やホテルへ出向く出張金継ぎワークショップを実施しています。
昨年は80名規模のワークショップを行い、日本の伝統文化を感じながら、チームメイト同士の親交を深める機会を提供しました。
SDGsにかなった伝統技法としても注目
金継ぎは、サステナブルな伝統技法としても注目されています。
壊れたものを捨てずに直して使い続ける姿勢は、SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」に貢献します。
今回の婚活イベントでも、シーグラスやシー陶器(海岸で見つかるガラス片・陶器片)を組み合わせ、金継ぎ風の箸置きへとアップサイクルする簡易ワークショップを実施しました。
欠片にシーグラスを呼び継ぎした器
本来の金継ぎは同じ器の破片同士をつなぎますが、欠片が大きく足りない場合には、別の器の破片を合わせて継ぎ直す「呼び継ぎ」という技法があります。
呼び継ぎは、異質なもの同士が「一度くっついたら離れない」とされる縁起物で、平和の象徴や、家庭の調和を願って施されてきたともいわれています。
そうした背景を踏まえ、今回のワークショップで生まれた、世界にひとつの呼び継ぎ箸置きが、将来一緒に食卓を囲むご縁へとつながっていくことを願っています。
つぐつぐでは、通常は天然の漆を用いた伝統金継ぎを行っています。
しかし伝統金継ぎは工程が多く難易度も高いため、短時間で行うのが難しく、「敷居が高そう」というお声も少なくありません。
そこで入口として、今回のような金継ぎ風のワークショップもご用意しています。
なお、金継ぎ風のワークショップで使用する接着剤は食器への直接使用を想定していません。
そのため、実際に食器を修復する際は、必ず食器にも安心して使える自然の漆による伝統金継ぎを採用します。
つぐつぐでは、今回のイベントのような1時間の金継ぎ風のワークショップだけでなく、90分の伝統金継ぎワークショップ、趣味として長く通える伝統金継ぎ教室を行い、一般の方でも金継ぎできるように指導しています。
そして「自分では難しい」と感じる方のために、プロ金継ぎ師に金継ぎを依頼できる、修理サービスも提供しています。
大切な器が割れてしまったとき、「捨てるしかない」と考えるのではなく、金継ぎしてまた長く使う選択肢があることを知っていいただければ幸いです。
最後に
この記事を読んで、金継ぎについて少し興味を持ったけど、本物の金継ぎ器をまだご覧になったことがない方は多いと思います。
つぐつぐのプロ金継ぎ師が金継ぎし、さらに芸術的になった器
9月11日~15日、東京・新御茶ノ水駅近くで「つぐつぐ金継ぎ作品展2025」を開催します。
昨年に続く2回目の今年は規模を拡大し、つぐつぐの金継ぎ教室の生徒とプロの金継ぎ師・漆芸家による、合計100点以上の金継ぎ器を展示する予定です。
それだけではありません。
会期中に、今回のイベントと同じ金継ぎ風ワークショップを当日受付でご体験いただけます(有料) 。
さらに、割れた器をご持参いただくと、予約制の無料お見積り相談会で修理可否と修理費用をご案内し、ご希望に応じて金継ぎ師への修理依頼も承ります(要予約/見積無料)。
作品展示では、ただ美しく個性的な作品を並べるだけではありません。
「なぜ、手間暇をかけてまで直すのか?」――出展者それぞれの“金継ぎドラマ”も掲示し、金継ぎの価値をわかりやすくお届けします。
プロの金継ぎ師・漆芸家による金継ぎ作品は、購入もできます。
金継ぎをブームで終わらせず、文化にする。
つぐつぐは、モノだけでなく、伝統を継承し、あなたの心もつないでいきます。
つぐつぐ金継ぎ作品展2025の詳しい情報はこちら
https://ocha-navi.solacity.jp/gallery/event/563.html
これからも、金継ぎを通して、世の中に新しくて面白い企画をお届けし、
伝統をつないでいきます。
■ IBJ Matching
https://www.partyparty.jp/