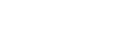「ハイチュウ」史上初!3つの味がひと粒になった50CHEW(周)年記念フレーバー「ハイチュウ<王道ミックス>」2月18日(火)より新発売
ハイチュウのパッケージデザインが消費者の感情に与える影響についての研究も実施
森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長・太田 栄二郎)は、心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディ「ハイチュウ」から、「ハイチュウ」史上初めて、ひと粒で3つのフレーバー(グレープ、ストロベリー、グリーンアップル)が楽しめる「ハイチュウ<王道ミックス>」を2月18日(火)より新発売いたします。
1975年に誕生した「ハイチュウ」は心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディで、日本だけでなく広く海外でも親しまれており、現在は世界30か国以上で販売しています。この度、”50CHEW(周)年”というアニバーサリーイヤーを記念して、今まで培ってきた当社の技術を最大限に駆使して、「ハイチュウ<王道ミックス>」を開発いたしました。またグローバルブランドとしてさらに世界観の統一を図るため、既存商品のパッケージデザインをスタイリッシュなデザインにリニューアル致します。新しいデザインにはハイチュウらしい遊び心のある仕掛けもご用意しております。これからも「ハイチュウ」は50CHEW(周)年を盛り上げて、世界中のお客様に笑顔をお届けしてまいります。
■「ハイチュウ<王道ミックス>」商品特長・「ハイチュウ」50年の歴史上初めて、3つの味が一度に楽しめる特別品質
・外側に巻いた層が2つのフレーバーに分かれており見た目も楽しめるカラフルな構造
・定番3フレーバー(グレープ、ストロベリー、グリーンアップル)のジューシーな味わいをひと粒で味わえる
・3種類のフルーツとハイチュウの断面シズルがインパクトのあるパッケージデザイン
▲粒のイメージ画像
▲商品画像
■パッケージデザインのリニューアルについて
・グローバル感のあるスタイリッシュさと独自食感を表現した柔らかなグラデーションをベースに、フレーバー毎の各要素(ロゴやフルーツの位置)を統一
・気づいたお客様に楽しんでいただける「ハイチュウ」ならではのワクワク感を表現した遊び心のある仕掛けをご用意
■「ハイチュウ」について
創業者の森永太一郎がアメリカで学んだキャラメルから発展し、1975年に誕生したのが「ハイチュウ」です。最初の「ハイチュウ」はソフトな食感とフルーツのおいしさをあわせた大人向けのお菓子として誕生しました。当時は箱入りで、粒は上下が白く真ん中にフルーツ色のキャンディを挟んだ3層構造でした。その後1986年に7粒入りの便利なスティックパックに、粒は”果汁本来の美味しさ、本物のフルーツを食べている時のような味”の変化を表現するため、外側と内側の二重構造の「あんこ巻き」になりました。外側はフレッシュ感や香りを重視した味わい、内側は果汁そのものの味わいを重視して仕上げており、外側と内側が口の中で融合することで、本物のフルーツを食べているようなフレッシュな味わいを表現しています。2013年には中と外の層を逆転させ、濃厚なフルーツの味わい層を外側にすることで、噛み出しから広がるフルーツ感が強化されました。そしてこの度発売する「ハイチュウ<王道ミックス>」は、原料と配合バランス、練り上げ時間や温度など綿密に調整する必要がある層に2種類の異なるフレーバーを組み合わせることに成功し、ひと粒に3つのフレーバーを入れることが実現いたしました。これからも「ハイチュウ」は進化を続け、驚きと楽しさをご提供してまいります。
▲<王道ミックス>製造工程の様子
ハイチュウのパッケージデザインが消費者の感情に与える影響についての研究
1000人規模の消費者研究により、ハイチュウのパッケージデザインが消費者の購買意欲に与える影響を評価しました。新パッケージのTease※1要素が消費者のポジティブな感情を引き出すことが明らかになりました。
※1Tease:いたずらのこと、今回の場合はデザインの“仕掛け“
■研究概要
本研究では、サイコメトリクス※2の手法を用いて、「SORモデル(Stimulus-Organism-Responseモデル)」を活用してパッケージ評価を行いました。SORモデルは、外部からの刺激が個人の内的要因を通じて最終的な反応を引き起こすプロセスを指し、消費者の購買意思決定プロセスを理解し、マーケティング戦略を立てるために活用されています。具体的には、消費者の購買行動を「刺激(Stimulus)」、「生体内条件(Organism)」、「反応(Response)」の3つの要素に分けて分析します。
・刺激(Stimulus):パッケージが消費者に与える情報
・生体内条件(Organism):刺激に対する消費者の感情や認知などの内部プロセス
・反応(Response):具体的な購買行動、愛着度、推奨度、口コミ意欲など
※2サイコメトリクス(心理測定学)とは:
心理的特性を測定・評価するための理論と技法を研究する分野です。具体的には、アンケートやテストを用いてデータを収集し、統計的に分析することで、個人の心理的特性を数値で評価します。この手法は、教育、臨床心理学、組織心理学などの分野で応用されています。
■研究方法
1000人規模の消費者調査によって、ハイチュウの現行パッケージ・新パッケージがどのような刺激を与え、それが最終的にどのような行動を引き起こすのか推定しました。
・Study1 現行パッケージを用いて、ハイチュウのパッケージにおけるSORモデルを作成(探索的モデル)
・Study2 現行パッケージを用いて、Study1で作成した探索的モデルの確からしさを検証(確証的モデル)
・Study3 Study2の確証的モデルをベースに、新パッケージのTeaseの効果を検証
■研究結果
現行パッケージと新パッケージの共通点として、消費者のポジティブな反応を引き出すために重要な5つの要素が確認されました。それは、「品質の高さや信頼感(Perceived Quality)」、「見た目の良さ(Package Appearance)」、「五感に訴える魅力(Sensory Appeal)」、「感情に訴える魅力(Mood)」、「おいしさの想起(Reward)」です。さらに、新パッケージにはTeaseが含まれており、これが商品の価値観を損なうことなく、「親しみやすさ(Familiarity)」を有意に少しだけ向上させ、「新奇性(Novelty)」も少し向上させる傾向があることが分かりました。
なお、Teaseは、消費者が商品上の“遊び”と捉える範囲を超えるとネガティブな感情を誘発することが知られていますが、今回の新パッケージにおいてはネガティブな要素は確認されず、商品をわずかに親しみやすく、新しいものに感じさせるというデザインの価値にポジティブな影響のみが加わる結果となりました。
▲ハイチュウの価値を表すSORモデル
▲Teaseによる 親しみやすさ(Familiarity)と新奇性(Novelty)への影響
■中央大学 檀教授コメント
今回の研究で用いたサイコメトリクスは、入念に設計された一連の質問、つまり「人の心を測る物差し」によって、人の思考を定量化する技術です。この実験では、徹底的に練られた質問の回答結果を、多変量解析などの高度な統計学的手法を用いて解析することで、ハイチュウのブランドや購買意欲に関する人々の認知構造をモデル化することに成功しました。これにより、味だけでなくパッケージからの情報や印象についても、お客様とのコミュニケーションをより深く理解することが可能となりました。特に、新パッケージのちょっとした仕掛けが、商品の価値を損ねることなく、「ちょっぴり親しみを上げた」という点は重要です。長年親しまれた商品への安定的な価値観を維持しつつ、半歩前進が可能ということが分かったのは、堅実なマーケティング戦略の効果を可視化する上で重要です。今回の研究で、ハイチュウをさらに活性化させるための新たな切り口が得られ、今後の商品進化が期待されます。
檀 一平太教授のご経歴中央大学 理工学部 人間総合理工学科 応用認知脳科学研究室 教授
脳科学と食品科学の融合分野の開拓に従事し、現在の主な研究テーマは、ニューロマーケティング、生理心理学、および、心理統計学による食生活QoLの解析等。
森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長・太田 栄二郎)は、心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディ「ハイチュウ」から、「ハイチュウ」史上初めて、ひと粒で3つのフレーバー(グレープ、ストロベリー、グリーンアップル)が楽しめる「ハイチュウ<王道ミックス>」を2月18日(火)より新発売いたします。
1975年に誕生した「ハイチュウ」は心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディで、日本だけでなく広く海外でも親しまれており、現在は世界30か国以上で販売しています。この度、”50CHEW(周)年”というアニバーサリーイヤーを記念して、今まで培ってきた当社の技術を最大限に駆使して、「ハイチュウ<王道ミックス>」を開発いたしました。またグローバルブランドとしてさらに世界観の統一を図るため、既存商品のパッケージデザインをスタイリッシュなデザインにリニューアル致します。新しいデザインにはハイチュウらしい遊び心のある仕掛けもご用意しております。これからも「ハイチュウ」は50CHEW(周)年を盛り上げて、世界中のお客様に笑顔をお届けしてまいります。
■「ハイチュウ<王道ミックス>」商品特長・「ハイチュウ」50年の歴史上初めて、3つの味が一度に楽しめる特別品質
・外側に巻いた層が2つのフレーバーに分かれており見た目も楽しめるカラフルな構造
・定番3フレーバー(グレープ、ストロベリー、グリーンアップル)のジューシーな味わいをひと粒で味わえる
・3種類のフルーツとハイチュウの断面シズルがインパクトのあるパッケージデザイン
▲粒のイメージ画像
▲商品画像
■パッケージデザインのリニューアルについて
・グローバル感のあるスタイリッシュさと独自食感を表現した柔らかなグラデーションをベースに、フレーバー毎の各要素(ロゴやフルーツの位置)を統一
・気づいたお客様に楽しんでいただける「ハイチュウ」ならではのワクワク感を表現した遊び心のある仕掛けをご用意
■「ハイチュウ」について
創業者の森永太一郎がアメリカで学んだキャラメルから発展し、1975年に誕生したのが「ハイチュウ」です。最初の「ハイチュウ」はソフトな食感とフルーツのおいしさをあわせた大人向けのお菓子として誕生しました。当時は箱入りで、粒は上下が白く真ん中にフルーツ色のキャンディを挟んだ3層構造でした。その後1986年に7粒入りの便利なスティックパックに、粒は”果汁本来の美味しさ、本物のフルーツを食べている時のような味”の変化を表現するため、外側と内側の二重構造の「あんこ巻き」になりました。外側はフレッシュ感や香りを重視した味わい、内側は果汁そのものの味わいを重視して仕上げており、外側と内側が口の中で融合することで、本物のフルーツを食べているようなフレッシュな味わいを表現しています。2013年には中と外の層を逆転させ、濃厚なフルーツの味わい層を外側にすることで、噛み出しから広がるフルーツ感が強化されました。そしてこの度発売する「ハイチュウ<王道ミックス>」は、原料と配合バランス、練り上げ時間や温度など綿密に調整する必要がある層に2種類の異なるフレーバーを組み合わせることに成功し、ひと粒に3つのフレーバーを入れることが実現いたしました。これからも「ハイチュウ」は進化を続け、驚きと楽しさをご提供してまいります。
▲<王道ミックス>製造工程の様子
ハイチュウのパッケージデザインが消費者の感情に与える影響についての研究
1000人規模の消費者研究により、ハイチュウのパッケージデザインが消費者の購買意欲に与える影響を評価しました。新パッケージのTease※1要素が消費者のポジティブな感情を引き出すことが明らかになりました。
※1Tease:いたずらのこと、今回の場合はデザインの“仕掛け“
■研究概要
本研究では、サイコメトリクス※2の手法を用いて、「SORモデル(Stimulus-Organism-Responseモデル)」を活用してパッケージ評価を行いました。SORモデルは、外部からの刺激が個人の内的要因を通じて最終的な反応を引き起こすプロセスを指し、消費者の購買意思決定プロセスを理解し、マーケティング戦略を立てるために活用されています。具体的には、消費者の購買行動を「刺激(Stimulus)」、「生体内条件(Organism)」、「反応(Response)」の3つの要素に分けて分析します。
・刺激(Stimulus):パッケージが消費者に与える情報
・生体内条件(Organism):刺激に対する消費者の感情や認知などの内部プロセス
・反応(Response):具体的な購買行動、愛着度、推奨度、口コミ意欲など
※2サイコメトリクス(心理測定学)とは:
心理的特性を測定・評価するための理論と技法を研究する分野です。具体的には、アンケートやテストを用いてデータを収集し、統計的に分析することで、個人の心理的特性を数値で評価します。この手法は、教育、臨床心理学、組織心理学などの分野で応用されています。
■研究方法
1000人規模の消費者調査によって、ハイチュウの現行パッケージ・新パッケージがどのような刺激を与え、それが最終的にどのような行動を引き起こすのか推定しました。
・Study1 現行パッケージを用いて、ハイチュウのパッケージにおけるSORモデルを作成(探索的モデル)
・Study2 現行パッケージを用いて、Study1で作成した探索的モデルの確からしさを検証(確証的モデル)
・Study3 Study2の確証的モデルをベースに、新パッケージのTeaseの効果を検証
■研究結果
現行パッケージと新パッケージの共通点として、消費者のポジティブな反応を引き出すために重要な5つの要素が確認されました。それは、「品質の高さや信頼感(Perceived Quality)」、「見た目の良さ(Package Appearance)」、「五感に訴える魅力(Sensory Appeal)」、「感情に訴える魅力(Mood)」、「おいしさの想起(Reward)」です。さらに、新パッケージにはTeaseが含まれており、これが商品の価値観を損なうことなく、「親しみやすさ(Familiarity)」を有意に少しだけ向上させ、「新奇性(Novelty)」も少し向上させる傾向があることが分かりました。
なお、Teaseは、消費者が商品上の“遊び”と捉える範囲を超えるとネガティブな感情を誘発することが知られていますが、今回の新パッケージにおいてはネガティブな要素は確認されず、商品をわずかに親しみやすく、新しいものに感じさせるというデザインの価値にポジティブな影響のみが加わる結果となりました。
▲ハイチュウの価値を表すSORモデル
▲Teaseによる 親しみやすさ(Familiarity)と新奇性(Novelty)への影響
■中央大学 檀教授コメント
今回の研究で用いたサイコメトリクスは、入念に設計された一連の質問、つまり「人の心を測る物差し」によって、人の思考を定量化する技術です。この実験では、徹底的に練られた質問の回答結果を、多変量解析などの高度な統計学的手法を用いて解析することで、ハイチュウのブランドや購買意欲に関する人々の認知構造をモデル化することに成功しました。これにより、味だけでなくパッケージからの情報や印象についても、お客様とのコミュニケーションをより深く理解することが可能となりました。特に、新パッケージのちょっとした仕掛けが、商品の価値を損ねることなく、「ちょっぴり親しみを上げた」という点は重要です。長年親しまれた商品への安定的な価値観を維持しつつ、半歩前進が可能ということが分かったのは、堅実なマーケティング戦略の効果を可視化する上で重要です。今回の研究で、ハイチュウをさらに活性化させるための新たな切り口が得られ、今後の商品進化が期待されます。
檀 一平太教授のご経歴中央大学 理工学部 人間総合理工学科 応用認知脳科学研究室 教授
脳科学と食品科学の融合分野の開拓に従事し、現在の主な研究テーマは、ニューロマーケティング、生理心理学、および、心理統計学による食生活QoLの解析等。